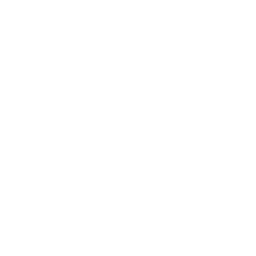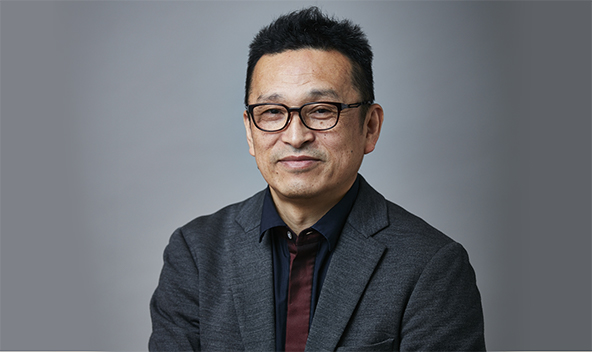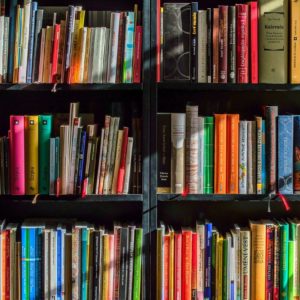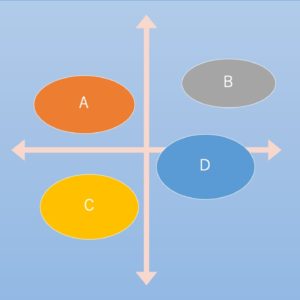2025年5月3日
シェアする社会への進化
こんにちは。ディープビジョン研究所です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
今回はブランド戦略コンサルタントの江上隆夫が
「シェアする社会への進化」
というテーマでお話しします。
それでは早速どうぞ!
★
Wiredに手持ちの服やスピーカーを貸して、
年間500万円を超える収入を手にするものも出る、
人気アプリがある、とありました。
これはアメリカの「Pickle」というアプリ。
そう、実際に所有しなければならないものは
案外、少ないものです。
私は、2018年に実家の全面リフォームを
することになり、家の大掃除を行いました。
何をどれくらい捨てるか?
想定したのは「家の9割はごみ」(笑)
で、作業を始めると実際にその通りでした。
1階にキッチンと居間、仏間とバス・トイレ。
2階に八畳間と六畳間の二部屋。
この小さな2階建てから出るわ出るわ。
2トントラックに山積み2台分のごみがでました。
あとに残ったのは食器・キッチン用品、文具類と日曜工具、
家族の写真やビデオ、寝具、タンス二棹、衣類、書籍。
4畳半に十分収まるだけになりました。
そんなものです。
不要なものと暮らしているんだなあと、
しみじみ思ったものです。
たぶん、環境意識が高く、
所有に意味を見出せなくなったZ世代以下から
シェアリングすることが当たり前になっていくのだろう。
「モノの図書館」を実現しようとしている友人がいます。
あらゆるモノが貸し借りできる
シェアリングエコノミーの権化のような施設。
10年もすると多くの耐久消費財は
サブスク型、リース型になっていく。
売るのではなく使ってもらって回収、再生、新製品。
モノは使って評価されて初めて認知される。
そういうエコノミーでは企業は
大きく戦略を変えなければなりません。
そろそろ準備を始めた方が
よいのではないでしょうか。
★
いかがでしたか。
日常的に使わないようなものだったり、
または特定の時期しか使わないような商品。
たとえば、赤ちゃん時に使うようなベビーサークルとか、
幼児期にのみ使用するようなおもちゃとか。
こういったものはまさにシェアがいいと思っています。
さらには、
成人したら出すことはないような雛人形とか5月人形とか、
もしかしたらこういった伝統行事にまつわる品も、
もう”所有”しなくてもいいのかもしれません。
日本は土地も住宅も狭いわりに、
伝統行事にまつわる品を含め荷物が多いと思います。
日本人は心理的にシェアが苦手な傾向にあると思うのですが、
でも、物理的に考えたら
日本こそシェアリングエコノミーが
実はマッチする気がしてなりません。
チャンスかもしれません。
それでは、次回のブログ更新もお楽しみに!