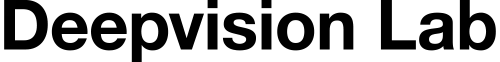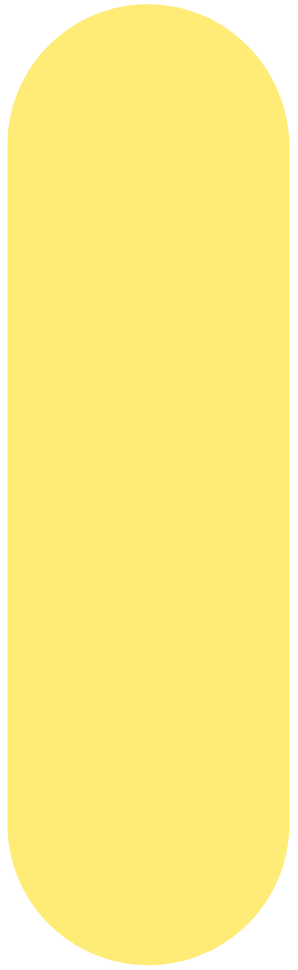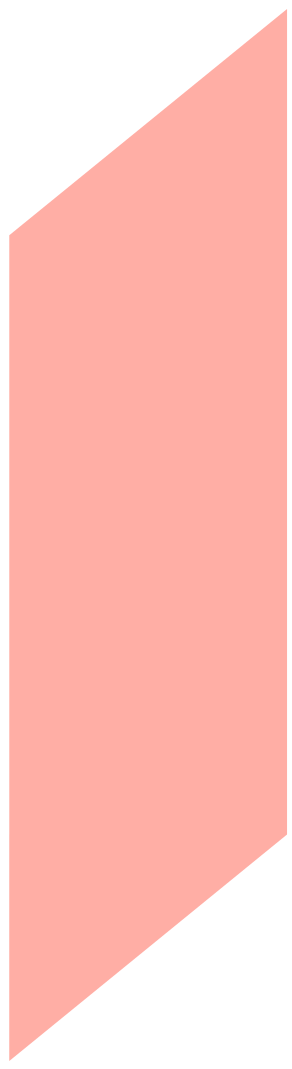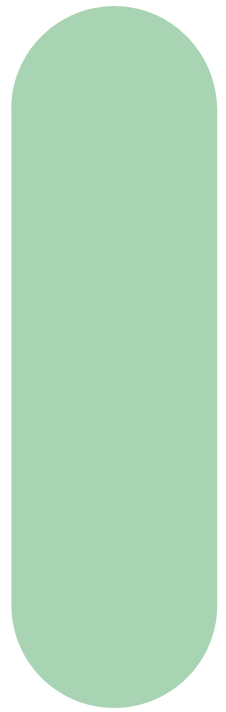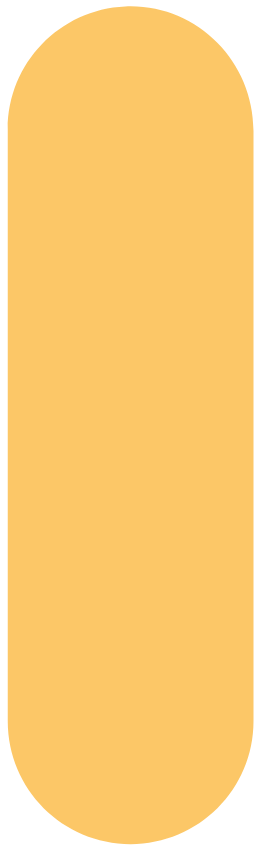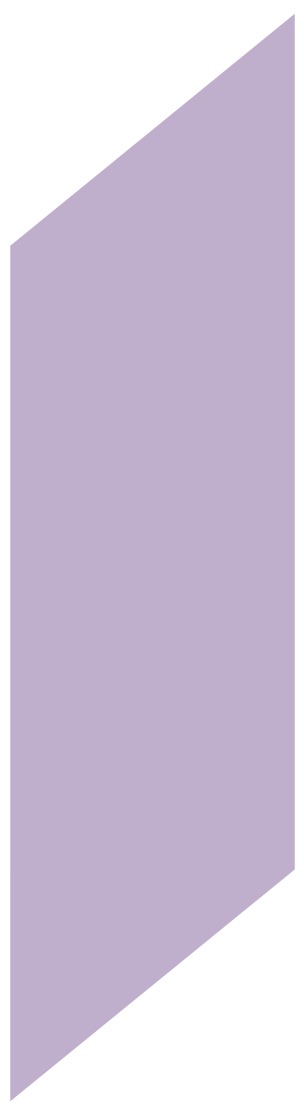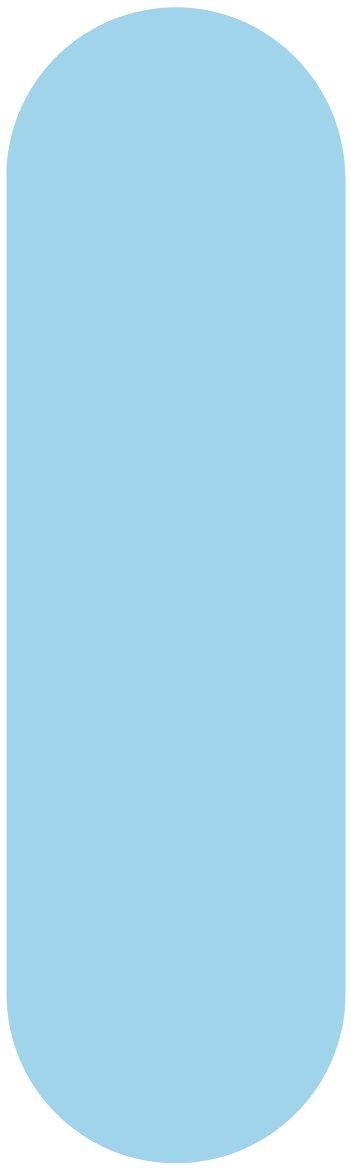2025.09.06
バイオミミクリー(Biomimicry):大自然から社会を構想する
こんにちは。ディープビジョン研究所です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
今回はブランド戦略コンサルタントの江上隆夫が
「バイオミミクリー:大自然から社会を構想する」
というテーマでお話しします。
それでは早速どうぞ!
★
次の社会のキーワードと考えられる
ことばはいろいろあります。
その一つに
「バイオミミクリー(Biomimicry)」
ということばがあります。
“みみくり”という音が
なんとも可愛らしいのですが(笑)
生命、生物、生物学を意味する「Bio」と
ものまね、模倣を意味する「mimicry」が
くっついた造語なんですね。
Biomimicryとは生物模倣あるいは
自然の模倣を意味しており・・・
思想的には
自然界の優れた構造、プロセス、
システムを模倣することで、
人類が直面する社会課題の解決を
目指そうとする概念です。
実は工業製品での生物の良いところを
取り入れるバイオミミクリーなことは
ずいぶん早くから行われています。
たとえばふだん私たちが
使っているマジックテープ。
あれはオオバコやゴボウの種子が動物の毛に
引っかかる仕組みをヒントにできたもの。
新幹線のノーズデザインも、
カワセミが水面に飛び込むときの
流線型をまねて、騒音を減らしつつ
高速化に成功しています。
アフリカのシロアリ塚の
通気システムを真似て、空調エネルギーを
ほぼ使わず温度調整ができる建物が
つくられたりしています。
私たちが欲しいものは、
自然の中に、大自然が数十億年かけて
実験を繰り返し、省エネで、超高機能で
柔軟性に富む素晴らしい生体システムとして
ほぼ、もう存在している可能性があります。
私が夢想するのは
次の社会システムのヒントが
こうした大自然の中にないのか?
ということです。
ミツバチの群れの意思決定のやり方。
魚の群れや渡り鳥の集団的知能。
腸内の菌叢の棲み分けの仕組み。
森の生態系の競争と共創のバランス。
サンゴ礁の多様なプラットフォーム性。
他にもたくさん出てきそうだけど
幸せに80億人が生きる方法が
まったく見つけられない人間としては
こうしたスゴイ仕組みを解きあかして
活用できないものか。
彼らを研究して、そのエッセンスが
社会設計に取り入れられれば・・・
もう少し穏やかな、
もう少し平和が続く、
もう少し幸せで、
そして、もう少し際限なき欲望と
折り合いを付けられる社会に
なれるのではないか。
久々の最高気温30度以下に
ホッとしつつ、そう思っています。
どうか大自然の神様!
我ら人類:困ったちゃんのために
ヒントをくださいませんでしょうか?
★
いかがでしたか。
私たちは体が勝手に呼吸をし、
総延長地球2周半とも言われる血管のすみずみに血液を流し、
栄養を取り込み余分なものを排出してくれる。
こんな高性能な機能が誰に教わらずとも、
体にインストールされ勝手に動いていてくれます。
じぶん1人とってもそうですが、
すべての生き物がそれぞれ
素晴らしいシステムを勝手に発動し、
この地球上の生命活動が行われている。
もう、すでに私たちが求める知恵は、
自然の中に組み込まれ、用意されている気がしてなりません。
それでは、次回のブログ更新もお楽しみに!