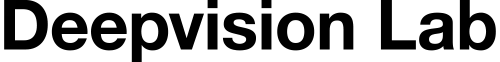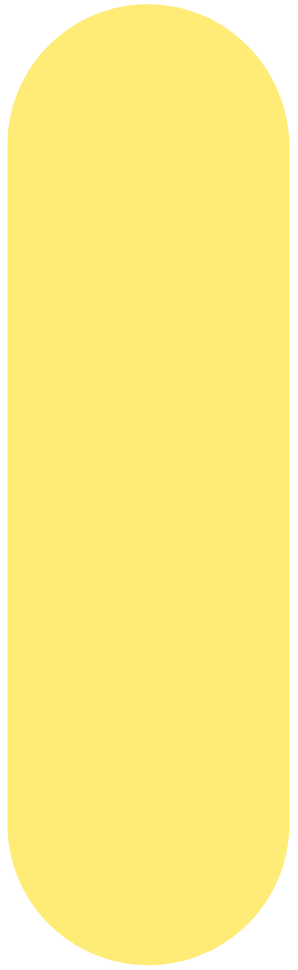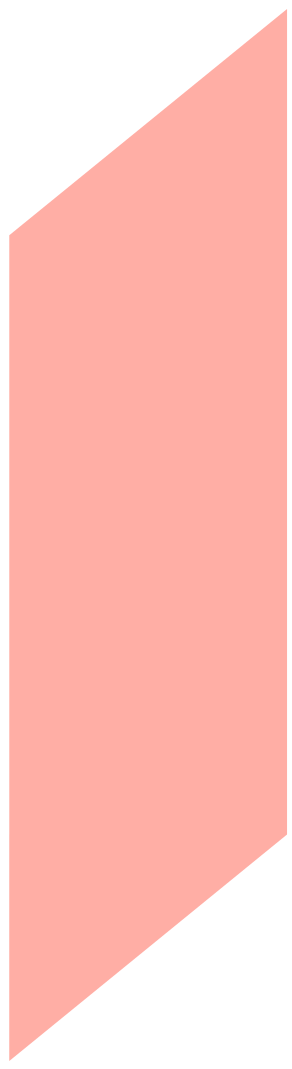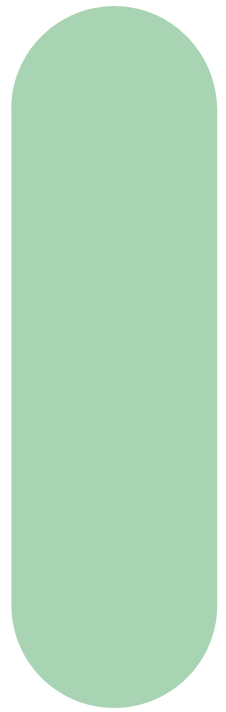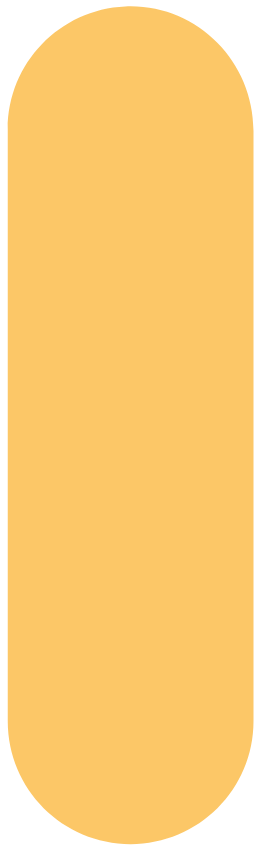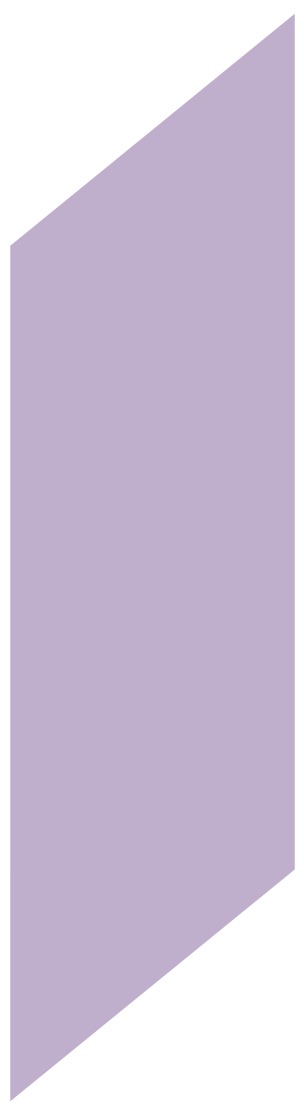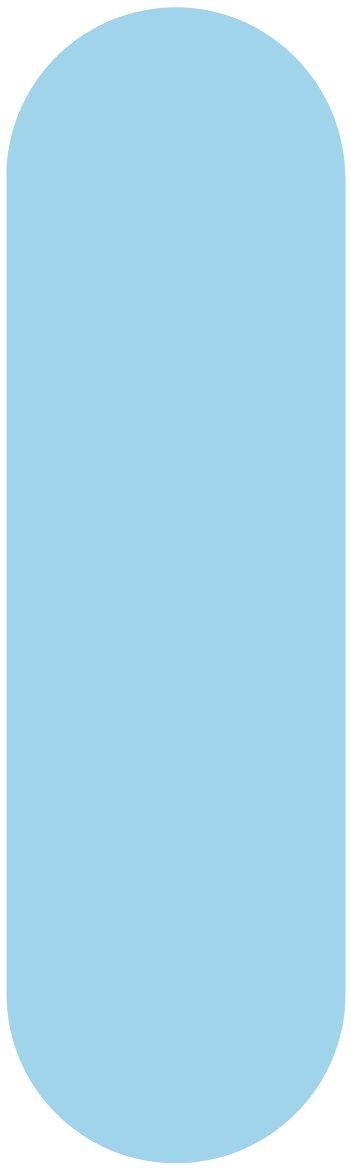2024.06.08
人間が集住し、都市が始まる
こんにちは。ディープビジョン研究所です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
今回はブランド戦略コンサルタントの江上隆夫が
「人間が集住し、都市が始まる」
というテーマでお話しします。
最近週末に連続してお伝えしている、
人間の歴史の第三弾!
これまでのテーマはこちら↓
・〈第一弾〉人類はなぜアフリカを出て世界へ散っていったのか?
・〈第二弾〉人類は農耕を始め文化を生み出しはじめる
第三弾、それでは早速どうぞ!
★
人間をどのような歴史の視点で見るか。
ふと自分のアイデアを知らせてたくなり、
週末メールマガジンでお伝えしています。
三週目です。
前週末はダンバー数を伝えました。
人間が互いを認知して集団として
機能する数は150名と言われていると。
しかし、このダンバー数が寄り集まり
紀元前5000年前ごろから
都市的な性格をもった集落が生まれるようになります。
つまり1000名とか数千名が暮らす「都市」が
出現するのです。
すると農耕の余剰が生まれ、余剰が富の概念に変わり、
富を管理する人が現れ、狩猟採集時代にはなかった
身分や職階のようなものが出現するようになります。
その土地土地で宗教と政治が発生し、
「文化」の洗練と高度化が始まります。
実験は世界各地で繰り広げられます。
その中でも巨大さを誇る実験は、
メソポタミア文明、エジプト文明
インダス文明、中国文明と呼ばれ
紀元前3000年から1500年の間に発展します。
どの文明も気候温暖な川の流域で栄えます。
このような文明ではなくても
世界各地の集団でさまざまなレベルで
文化の高度化を成し遂げていきます。
国家ができ、シンボルとしての王が現れ、
階級ができ、記録や呪術などのために
文字が生まれ、口伝以外で
文化の蓄積が可能になっていきます。
古代エジプトの人口は
紀元前500~300年あたりで300~400万人と
言われています。
ほぼ、この時代に現代につづく、
都市な在り方の基礎は
できあがっていたのではないかと思います。
個人的に、
都市は「人間の大規模集積回路」だと
考えます。
集積度が増すほど集積回路は
高性能になるように、集住することによって
専門職が発達し、有閑階級が出現し、
人間の営みのあらゆることが文化的な行動なものに
転換されていったのだと思います。
人類の実験が次のステージに入ったのですね。
この集住時代から
他地域との交易が始まります。
つまり拡散し、定着し、洗練が起こり、
さらに「異文化との交流」が始まったのです。
しかし、この交流が本格的に動き出すのは
大航海時代です。
次週へつづきます。
★
いかがでしたか。
農耕を始めた人間が、
都市を形成し始める流れが今回。
次回は大航海時代を経て
「異文化との交流」が始まります。
次週もお楽しみに!